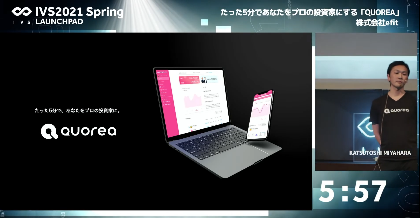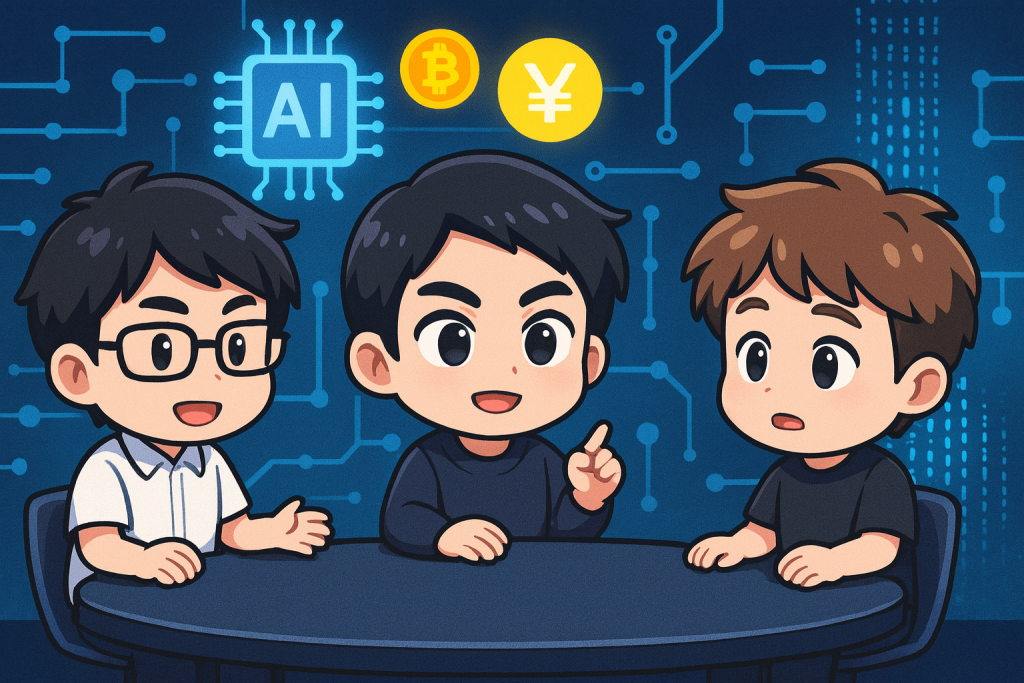
この記事は、YouTube動画の【川上量生vs仮想通貨】大激論!本当は損してる?暗号資産界隈の本音とは…【ReHacQ高橋弘樹vs加納裕三vs岡部典孝】の内容を分かりやすく纏めたものです。
ドワンゴ創業者の川上量生氏がSNS上で「暗号資産界隈の頭の悪さ」を指摘したポストが火種となり、業界の第一人者である加納裕三氏(ビットフライヤーCEO)、岡部典孝氏(JPYC代表取締役)らとの間で、暗号資産の是非を巡る激論が交わされました。
本記事では、この対談から明らかになった、暗号資産が抱える「本源的価値の不在」という構造的な問題と、ブロックチェーン技術が既存の金融システムにもたらす真のイノベーション、そして日本が直面している規制と競争の課題について詳解します。
暗号資産の価値と構造
川上氏の暗号資産への批判の核心は、その価値の根拠が不明確であり、構造的に先行者が利益を得やすい点にあります。
「本源的価値」の有無
川上氏は、金(ゴールド)が物理的な性質を利用した工業製品としての本源的価値を持つことに対し、仮想通貨の価値は「その値段で売れるからしかない」と断じます。株式の場合、最低限、利益還元(配当や残余財産分配請求権)というファンダメンタルズが価値の支えとなりますが、クリプトのほとんどにはそれがありません。
これに対し加納氏は、金の実需(本源的価値)も実際の価格の数パーセントに過ぎず、大半は「次の人が高く買うから今買っておこう」という投機的な性質に依存している点で、仮想通貨と似た側面があると反論します。
ただし、中にはサービス提供義務を負うなど、株のような計算方法が適用できるファンダメンタルズを持つトークンも存在すると分類されています。
先行者利益の構造
川上氏は、ブロックチェーンを用いたアプリケーションは「特権者が分かりにくく分散しているだけ」であり、最初にコミットした人が儲かるように設計されていると指摘します。
この構造はネットワークビジネス(マルチ商法)と非常に似ており、利用するインセンティブは「先に始めるとお金が儲かること」にあると分析しています。
岡部氏も、マルチ商法に近いと感じる構造があることを認めつつも、先行者利益の構造自体は株式など他のリスクを伴う業界にも存在すると述べています。
また、先行者が必ずしも儲かるわけではなく、プロジェクト失敗により損をしているケースも多数あるため、勝っている部分だけを見て評価するのは客観的ではないという意見もあります。
通貨発行権の問題
川上氏のもう一つの論点は、暗号資産が国家から通貨発行権を奪う行為である、という点です。国家は社会福祉やインフラ維持(警察、年金、道路建設)を担いますが、ブロックチェーンによって通貨発行益を手に入れた人たちは、そうした社会的責任を負わないのではないか、という懸念です。
法定通貨の発行は物価の安定や経済政策が目的とされますが、トークンの多くは営利目的で発行され、発行体が儲かる仕組みとなっています。
トークンには、ビットコインのように発行量を調整できないものと、自由に発行できるものがあり、さらにその中で発行体が義務を負うもの(サービス提供義務など)と、義務を負わないもの(ミームトークンなど)に分類されます。義務を負わないトークンは、資金調達がそのまま利益となる構図であり、「詐欺的」とも言えると指摘されています。
技術的優位性
暗号資産は投機の道具と見なされがちですが、専門家はブロックチェーンが既存の金融システムが持つ構造的な課題を解決する「黒船」として機能している点を強調します。
決済コストの削減
従来の国際送金(SWIFTなど)は遅く、カード決済手数料は日本国内で約3%と高水準です。
川上氏はシステムを作り直せば手数料は下げられると主張しますが、既存の法定通貨を動かすシステムには、マネーロンダリング対策(AML/CFT)やコンプライアンス維持に膨大なコストがかかっており、それが政治的な硬直性となってシステムを作り替えることを困難にしています。
ブロックチェーン技術は、この政治的な合意の難しさを避け、既存の金融システムインフラの1/100程度の低いコストで送金を提供できる可能性を示しています。
法規制を回避
ステーブルコイン(電子決済手段)が低コストでサービスを提供できる背景には、技術革新だけでなく、法律上の枠組みの変化があります。従来のプリペイドカード会社などに課せられる「加盟店管理義務」は、違法な商品の取引などを監視する義務であり、膨大なコストがかかります。
しかし、ステーブルコインはブロックチェーン技術を用い、不特定多数の誰でも平等に取引できる「デジタル現金」のような仕組みであるため、この加盟店管理義務が法的にない、という利点があります。
これにより、コスト削減が可能となるだけでなく、金融機関が一律に決済を停止する「金融検閲」のリスクを軽減し、表現の自由や人権を最大限に尊重する民主主義国家の原則に立ち返る役割も果たし得ると考えられています。
AI経済圏の基盤
ステーブルコインは、将来的にAIエージェントが自律的に決済を行うための「プログラマブルマネー」として期待されています。現在、AIエージェントは人間の秘書のように自動で買い物をするには至っていませんが、デジタルで誰でも使えるお金が必要とされています。
GoogleやOpenAIといったテック企業がステーブルコインを使ったAIエージェントの決済プロトコルを推進しており、約47兆円が流通するステーブルコイン市場では、取引高の約95%がAIによるものだと推測されています。
これは人間社会への貢献度はまだ低いように見えても、AIの世界での取引量が急速に拡大し、既にVisaやMastercardよりもステーブルコインの決済取引量が多い状況です。
規制と競争の課題
世界的なデジタルマネー競争が激化する中、日本は規制対応で遅れをとっており、金融インフラとしての脆弱性を抱えています。
日本の競争遅れ
世界のステーブルコイン市場の99%はドル建てであり、日本円のデジタルインフラとなる「電子決済手段」は、日本が2022年に規制を整備したにもかかわらず、普及が遅れています。
日本で初のライセンスを取得したJPYCも、ようやくスタートラインに立とうとしている段階であり、国際的な競争において不利な状況です。
インフラ買収リスク
日本円のデジタルインフラとなるステーブルコインの発行体が、国際競争に敗れたり、日本の投資家が集まらなければ、海外の投資家や敵対的な国に買収されるリスクが指摘されています。金融インフラとしての公共性が高いにもかかわらず、メディアのような外資規制がかかっていないため、投資家が関与しない場合、外国資本に主導権を握られる可能性があります。
脆弱性と信頼性
暗号資産の安全性についても議論が交わされました。ブロックチェーンは、書き換えができないという点で改ざんに対しては安全であるとされています。しかし、ビットコインなどの技術は「システム的には本当にクズ」であり、その価値は「ブランドバリュー」に依存しているという批判もあります。
また、仮想通貨で発生するセキュリティ事故のほとんどは、ブロックチェーン技術そのものの脆弱性ではなく、交換所(取引所)の内部システムや人間の脆弱性(フィッシング、内部不正)によって引き起こされています。
法定通貨を扱う既存金融機関では、データベースがハッキングされてもバックアップからデータを「戻せる」ため安全性が担保されますが、暗号資産取引所ではそれが困難な場合があり、信頼性の課題となっています。
加えて、トークン発行においては、上場した株式のような厳格な開示義務がなく、先行者利益や詐欺的な要素が絡むビジネスモデルが存在するため、発行体が資金を何に使ったのか(例:役員報酬、ブランド品購入など)が不透明であり、疑念を招きやすい構造となっています。
記事まとめ
川上量生氏が指摘する通り、暗号資産界隈には「本源的価値のない投機的な要素」や「マルチ商法に似た先行者利益の構造」が存在し、その多くは社会に価値を生み出していないという厳しい側面があります。
しかし一方で、ブロックチェーン技術、特にステーブルコインは、既存の金融システムが抱える政治的・構造的な高コスト問題や硬直性を打破し、AI時代における新たなデジタル経済の基盤、あるいは国際送金の効率化といった、社会的なインフラになる可能性を秘めています。
日本は現在、ステーブルコインの普及において国際的な遅れをとっており、このままではデジタル金融インフラの主導権を外国資本に奪われるリスクが指摘されています。
暗号資産を単なるマネーゲームで終わらせず、社会のインフラとして活用し、国際競争を勝ち抜くためには、事業者による透明性の確保と、国家による適切な規制(外資規制など)の導入が今後の鍵となると言えるでしょう。