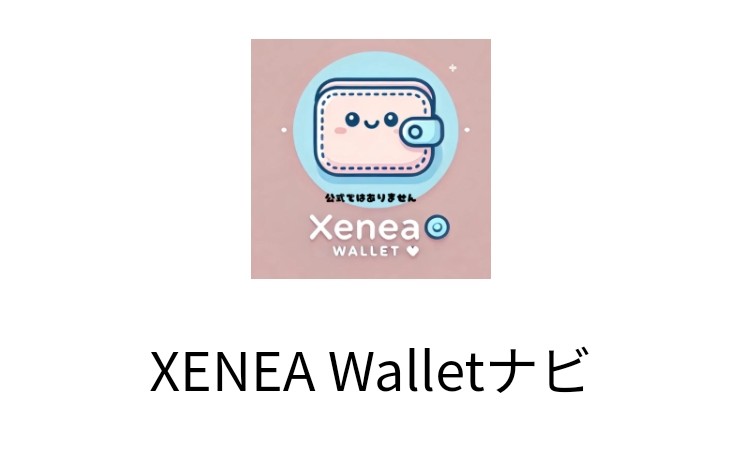2025年4月27日、韓国で開催されたDePINA Korea Cohort 0にて、XeneaのCSOであり共同創業者のYuma Tanimoto氏が登壇しました。このイベントには、FilecoinやAethirなどの有名プロジェクトも参加しており、彼のスピーチは大きな注目を集めました。
今回は、そのスピーチのポイントを、初心者にも分かりやすいようにAIで解説記事を生成しました! もし誤った情報がございましたら、ご連絡いただけますと幸いです🙇 まず、Xenea(ゼニア)は、未来に向けたデータ保管のインフラを作るプロジェクトです。特に注目なのが、単なるブロックチェーンではなく、動的なデータ(更新され続けるデータ)も安全に保管できる仕組みを取り入れている点です。 また、XeneaはEVM互換(Ethereumと同じ技術基盤)を持っているので、他のブロックチェーンプロジェクトとの連携もスムーズです。 スピーチの中で谷本氏が特に強調していたのは、 > 「分散化は技術的な状態。分配は社会的な仕組み。」 という言葉です。 簡単に言うと、「データをバラバラに置くのは技術でできるけど、それを持続的に運営する人を確保するのはとても難しい」ということです。 つまり、サーバーを置くだけじゃなく、そこに電気代を払ったり土地を維持したりする**「人」と「お金の流れ」**がなければ、本当の意味での分散型インフラは作れないという話ですね。 谷本氏は、過去の例として次のプロジェクトを紹介しました。 これらから導かれる教訓は、 > 「インセンティブ(報酬)が最初の勢いを作り、分配の仕組みが持続を支える。」 というもの。つまり、単なる「お金」だけではなく、仕組み作りが重要だということです。 谷本氏は「分配には3つのレイヤーがある」と語りました。 これら3つのレイヤーがしっかり機能すれば、分配(ディストリビューション)は止まらないとしています。 さらに、実際の取り組み事例も紹介されました。 これにより、「分散型インフラ」が単なる技術プロジェクトではなく、地域活性化や生活向上にもつながることが示されました。 最後に、谷本氏はこう締めくくりました。 > 「分散化は技術的には簡単。でも分配の仕組みを作るのが本当に難しい。だからこそ、今みんなで作っていこう。」 Xeneaは、単なるブロックチェーンではなく、未来の人々が安心して価値を受け継げる世界を目指しています。 彼らの挑戦はまだ始まったばかり。これからの展開にもぜひ注目していきましょう! 
Xeneaって何?
「分散化」と「分配」の違いとは?
成功と失敗から学んだ「持続のヒント」
分配を成功させる3つのポイント
「1人1票」が原則で、透明性が大事。
使いやすさが重要。日常の一部になること。
コストを地域でカバーし、利益も地域で分配すること。世界での実例紹介
まとめ|これからのXeneaの挑戦